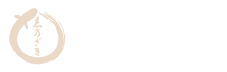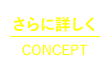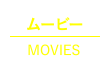引き裂かれてしまった「日常の声」と「音楽の声」
学校の音楽の授業で「頭に声を響かせて」とか「頭から釣られているように」という言葉で発声練習をなさった方も多いのではないでしょうか。これは、昭和26年以来、文科省(旧文部省)の学習指導要領に「喉に力を入れず頭に軽く当てる声」すなわち「頭声」こそ子どもに教えるべき声であると記載されて来たことに由来します。
しかし、世界の伝統にはそのような声はほとんどありませんし、当然、日本の伝統的な声とも違います。そのような声で音楽を行うのはウィーン少年合唱団に代表される教会の少年合唱団だけです。すなわち、ヨーロッパのカトリック教会で変声期前の男子を中心に構成される少年合唱団の発声なのです。
日本の戦後の合唱教育は、500年の歴史を持つウィーン少年合唱団の発声を「天使の歌声」だとして、これを日本の教育で行おうと思った戦後の若き音楽教師たちによって打ち立てらた方針で作られました。
確かにウィーン少年合唱団のアートは素晴らしいものです。しかしそれはとても限られた1ジャンルの声にすぎません。オペラの重唱ではもっとずっと喉に力の入った(声門をきちんと閉めた)発声をしますし、ミュージカルやポピュラーでは口の中をぐっと平らに潰して歌うことも珍しくありません。
頭声至上主義により、民謡や演歌で聴くような日本の伝統的な発声も教育現場から遠ざけられ、労働歌やわらべうたなどを学校で教えることもなくなってしまいました。学校では、あたかも「音楽の声と日常の声は違う」という話が正義かのように話されるようになってしまったのです。
本来、言語文化と歌は切り離せないものですので、これは一つの国の文化にとってとても破壊的なことです。学校で言うような意味で音楽の声と日常の声が違っているのは、私たちが異文化の音楽を学んでいるからにすぎないと言うことさえ、忘れられてしまったのです。
日本では、中二にもなると男子を中心に合唱離れが進み、「ちょっとー男子ー、ちゃんと歌いなさいよー」というあるあるジョークは、今の若い人たちにもよくウケます。声の個性を抑えて統一を目指すことで作る合唱だけが合唱だという価値観が長年学校で教えられ、日常生活で尊ばれる「元気な声」は、音楽には適さない声だとされて来ました。それでは、元気な声の持ち主たちが合唱から遠ざかるのは当たり前です。
しかし、すでに転機は訪れています。
平成23年の改訂で、学習指導要領から「頭声」の文字は一切消え去りました。今は「曲種に合わせた発声」を教えることが推奨されています。
90年代のゴスペルブームもまた、私たちに地声合唱の魅力を再発見させてくれました。大声で笑い、泣き、感情を表現する人々が、その声のままで自分が伝えたいことを思いっきり歌う。合唱ってこれでいいんじゃないか、こういう合唱がやりたかったんだ、そんな思いをゴスペルは私たちに抱かせてくれたのです(ただし、ゴスペルについては宗教感に関連する種々の理由からブームとしては衰退しました)。
2022年に始まったフジテレビの不定期特番「オールスター合唱バトル」でも、芸能人やアスリートなどによる力強い地声合唱が展開されています。
地声とビート感のある合唱は、私たちが歴史の最初から持っていた、人と人とを繋げる本来の「生活音楽」型の合唱であり、決して新しいものではありません。むしろ最も古い形の労働歌や、祭りや儀式の歌や、わらべ歌など、私たちの話す言語や歴史と密接な関わりを持った合唱の姿です。グローバル化や情報化、多様性への理解が進む中で、ウィーン少年合唱団型の頭声合唱も多様な音楽スタイルの一つにすぎず、まして決して正義などではないことが、やっと教育現場でも理解され始めています。
合唱とは本来、人が集まって歌うという「編成」の名前であり、音楽ジャンル名ではありません。そこにロックがあってもクラシックやジャズがあってもよく、人が集まり声を束にして歌う全ての音楽が合唱と呼ばれて然るべきです。
しかし戦後70年の教育の影響で日本では、合唱というとウィーン少年合唱団型の「頭声合唱」を思い浮かべてしまいます。
そのため、地声表現とビート感のある合唱には別の呼称が必要であろうという考えから、当協会では、パワーコーラスというジャンル名を提唱させていただいています。
ウィーン少年合唱団も、戦後教育型の頭声合唱も、パワーコーラスも、同様に「合唱」の一つの形です。